近江ARS 第2回龍門節会ダイジェスト
師の面影に寄せる
暦の上では処暑、日中の暑さが和らぎ、夜が長くなりはじめた9月上旬、瀬田川のほとり、叶 匠壽庵「寿長生の郷」を舞台に第2回目の近江ARS「龍門節会」が催された。今回、松岡正剛が設定したお題は「寄せる」。「何かに近づくこと、気持ちをそこに傾けること、そのためにいろいろなものを寄せ集めてみることが「寄せ」なのだ」(『見立て日本』松岡正剛)。松岡が常々日本文化の重要コンセプトの一つと述べてきた言葉である。
和泉佳奈子の発声で場が開かれた。「足を運んでくださった方々に“遊び”を尽くしてほしい」。近江ARSの会を開くたびに松岡が願ってきたことだ。叶 匠壽庵の芝田冬樹が松岡から託された言葉、「節会は大人の真剣な遊び」を紹介し、池田典子が「“節”という漢字がもつ“モノとモノを結び付ける”という意味を体現するような一日にしたい」と場に臨む覚悟を見せる。数週間前に旅立った松岡の言葉と姿を場に感じながら、遊びきる一日が始まった。


第1部|笑う門には
「果節の間」の壁に描かれた大きな太陽を背に落語の高座が設えられた。松岡が、毎度変化する語りを楽しみにしていたという柳家花緑師匠と弟子の柳家勧之助師匠が特別ゲストとして馳せ参じた。
最初に登壇した柳家勧之助師匠の演目は『青菜』。植木屋夫婦のずれた会話が徐々に加速する。勧之助師匠の声と表情も、「序」から「破」へと移り、一気に「急」に向かう。「鞍馬山から牛若丸が出でましてその名を九郎判官義経…」。勧之助師匠の目一杯の形相とともに疾風怒濤の幕が下りた。

続いて、軽やかな三味線の節にのって柳家花緑師匠が高座にあがる。真打昇進以来、30年を共にしてきた出囃子『お兼ざらし』は近江に由来するものだ。五代目柳家小さんを祖父にもち、戦後最年少の22歳で真打という華々しい経歴をもつ花緑師匠だが、ここまでの道は決して平坦だったわけではない。落語をはじめた9歳から現在までの自身の歩みと30年に及ぶ松岡との縁とを振り返りつつ、今回は師弟を描いたこの演目しかないと『百年目』を語りはじめた。
普段は硬い顔をして店の小僧たちに口やかましく小言を言う番頭が、花見で羽目を外している姿を大旦那に見られてしまう。花緑師匠の声色から、番頭の茫然自失が手に取るように伝わってくる。翌日、番頭を呼び出した大旦那が、栴檀(せんだん)と南縁草(なんえんそう)の逸話をはじめる。花緑師匠の表情と声が、少しばかり重厚感を纏う。この落語の見せ場だ。美しい栴檀をいっそう楽しむためにと、あるとき根元の汚い南縁草を刈り取った。すると、栴檀がたちまち弱って枯れてしまった。栴檀は南縁草を肥やしに成長し、南縁草は栴檀から降りる露によって育っていた。「無駄をどんどんと切っていったら本当に世の中は良くなっていくのだろうか」と大旦那が番頭に問う。番頭はもちろん、会場の誰もが心中で首を横に振る。「役に立たないと思った者でも、じっくり腰を据えて育ててほしい」と諭すように大旦那が話す。番頭にも会場にも安堵が広がる。和やかに話が終わるかと思いきや、「ところであの日のお前さんの踊りは上手かったなぁ」と大旦那が踊りだす。ふたたび笑いの渦が起き、大きな拍手に包まれて、花緑師匠が高座を降りた。


第2部|セイゴオ寄せ
大きな窓ガラスから明るい光がさす広間へと場所を移ると、目に入るのは、一風変わった床の間である。学芸員の横谷賢一郎が松岡のために設えた「千夜千床」だ。叶 匠壽庵の芝田冬樹が用意した薯蕷饅頭「光琳菊」と三井寺執事の福家俊孝が淹れた三井寺茶が供えられる。客人たちにも、菓子と茶が振舞われると、横谷による室礼語りがはじまった。床の右手に配されたのは、ウィルソン・ベントレーによる雪の結晶の写真だ。千夜千冊第1夜『雪』の中谷宇吉郎が大きな影響を受けた写真家だ。中央には、和漢朗詠集の軸。松岡は「和漢の境をまぎらかす」ことを大切にした。慣れ親しんだ評価を超えて別の評価軸を持ち込んでこそ新たな価値を生むことができる。松岡のあり方を象徴するものとして、横谷が数ある軸のなかから選び抜いた。その左に添えられたのは瓢箪。最後の千夜千冊第1850夜『中国人のトポス』には「瓢箪をのぞいてみれば別宇宙」と記されている。松岡による瓢箪語りとも言える千夜千冊だ。
福家俊孝が横谷に続く。三井寺の古い茶の木を活かしたいと、お茶づくり・お茶淹れに取り組む俊孝に「よかったよ、続けたらいい」と松岡は声をかけ続けた。「松岡さんの言葉があったから今がある」という俊孝の言葉に、『百年目』の大旦那の度量の広さが思い起こされた。一同が名残惜しむように室礼を味わった後、場所は次の間へとうつる。



第3部|芭蕉と座
「風来の間」に踏み入れると、舞台上の淡い葡萄の水墨画に客人たちの目が奪われる。「少数なれど熟したり」。松岡は、この数学者ガウスの言葉を座右の銘とし、事務所の壁にもラテン語で「Pauca sed Matura」を掲げ続けた。葡萄は一つの株からたくさんの房をつける。が、濃厚な味わいのワインとなる葡萄とするためには、数を絞ることが肝要となる。ガウスも松岡も、多くの発見をしていながら、これというものを極め尽くした。その生き方を横谷が葡萄に託した。
「芭蕉と松岡さんは重なるのではないか」。葡萄の脇に立った三井寺長吏の福家俊彦が、胸の内に秘めていた問いをもちだして、芭蕉語りをはじめた。俳諧は、日常的な言葉を使いながら日常世界の見え方を変えていくことに妙味がある。そして、多くの人々と連なって行なう座の文芸でもある。個として言葉の究める孤高と人々と和するための普遍性、芭蕉はこの両者の間で引き裂かれそうになっていただろう。そんな芭蕉にとって、旅は両者の間を埋め新たな方向性を見出す機となる特別なものだったに違いない、福家が仮説する。前人未到の道を行くのは並大抵のことではない。松尾芭蕉、そして、松岡正剛、二人の先人に倣って近江ARSも進まねばならないと改めて宣言した。
福家に呼ばれて、文芸評論家の安藤礼二氏が舞台上にあがった。著作『折口信夫』(2015年発刊)を松岡が称えてくれ、出雲への学びの旅を共にしたことがある。「“私”をゼロにすることで色々な力を呼び込み、“私”を全く異なるものに変えていけるのが表現の可能性。松岡さんが体現していた“編集“もまさにそれです。芭蕉と松岡正剛さん、時間を超えて二人を結びつけて語れる時期がきました」と迸るように語った。


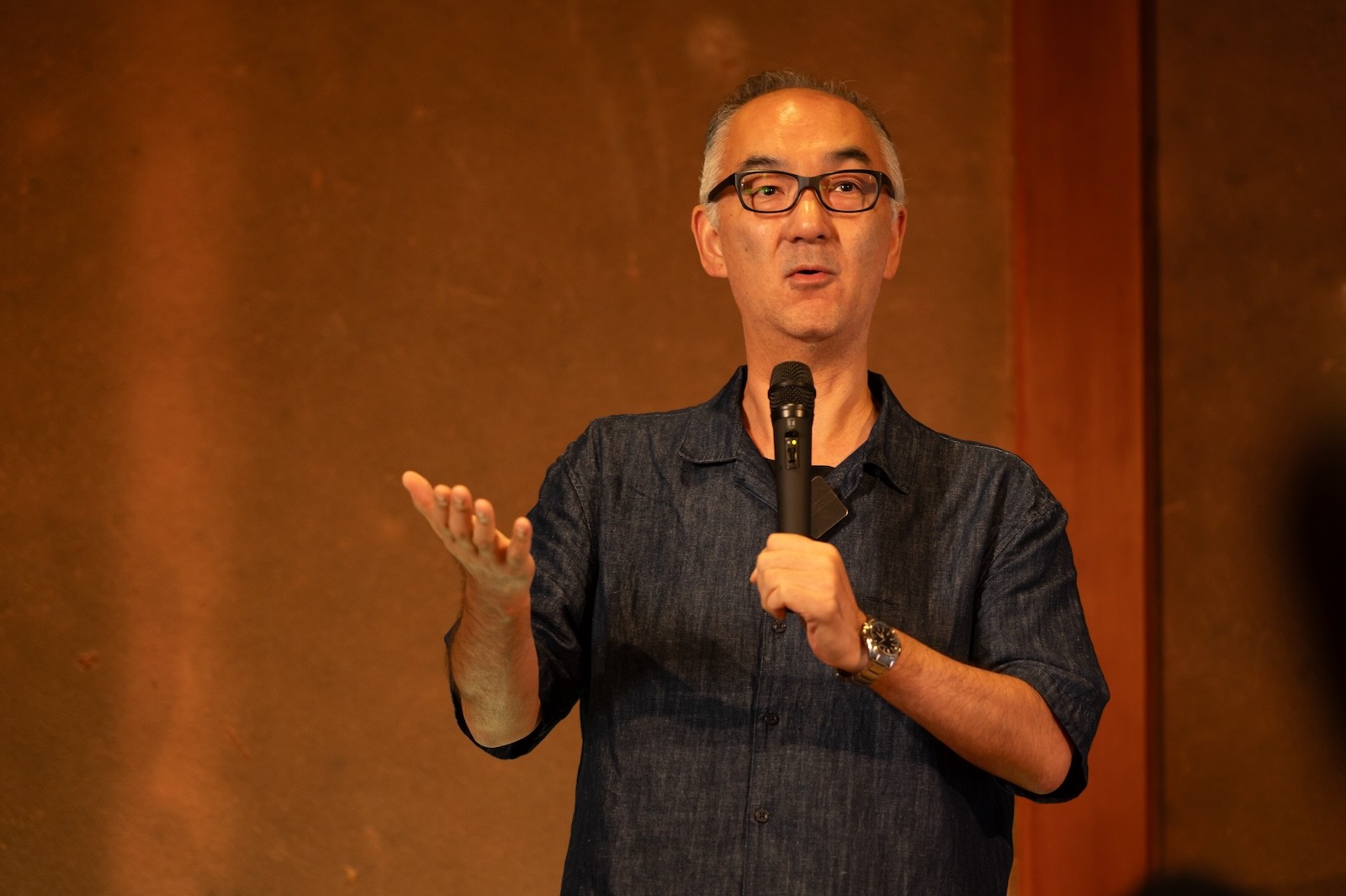
第4部|弟子は師匠なり
ふたたび「果節の間」へと会場がうつる。少し早くなった日没で、辺りが闇に包まれはじめた。節会の最終章は、柳家花緑師匠、柳家勧之助師匠、和泉佳奈子の3人による鼎談だ。
祖父の5代目柳家小さんが亡くなってから早くも22年の月日が経つ。にもかかわらず、花緑師匠にとっては、年々「祖父との距離が近くなっている」そうだ。生前は距離感をはかることもあったが、今は近づきたいだけ近づくことができる。先輩やお客さま、さらには本を通して、自分のほうから小さん師匠を感じたり探したりするようにもなった。修行を重ねて守破離と進み、自分の話に一切の責任をもつ「離」の段階に到達したのちも、「自分で自分の芸をいつなんどきも見直すように」と小さん師匠は言い続けた。「これでいいと思ったら落語が死んでしまう」。セリフの順番を入れ替える、セリフをそぎ落とす、話し方を変える。新鮮さを保つために、常に自分のほうから話を動かしていく。決して編集をやめない。
師についての話題は尽きない。最初の弟子を取るときに、「教えることは学ぶことだから弟子を取りなさい」と小さん師匠が花緑師匠の背中を押した。4人目の弟子を取る頃になって、「弟子は師匠なり」という小さん師匠の言葉が実感を伴ってきたという。はじめの頃は、弟子に何を言うべきかを考えていた。あるときから、自分がどうあるかを大切にするようになった。こういう落語がいいと言いたいなら、自分がそれをできているか。感謝が大切というなら、自分がありがとうと言っているか。常に弟子に見られてよい自分であるか。すべてを弟子に見せる覚悟をした途端、弟子との時間が充実し、教えることが楽しくなった。和泉が大きく頷く。松岡は、編集を終えようとしているものにあらがうことを自分にも周囲にも課した。だからこそ、花緑師匠の変え続ける姿に大きな可能性を感じ、応援し続けたのだ。周囲がすっかり暗くなるまで話が続いた。


4月の近江ARS TOKYOを象徴する『近江いろは歌』にしばし耳を傾け、散会となった。帰路につく面々に、季節の菓子と寿長生の郷に自生する黒文字で仕立てた楊枝が手渡される。叶 匠壽庵の面々が、一つひとつ手で仕上げたものだ。松岡から託された言葉と方法に肖って、最後まで「数寄」を遊びきる。21世紀の新たな“節会”に集った一人ひとりが、場に寄せられたもの・集められたものを通して、師の面影を胸を傾け、各々の数寄と方法を磨くことを誓いあう一日となった。

ーーーーー
-出演-
落語家 柳家花緑
落語家 柳家勧之助
叶匠壽庵代表取締役社長 芝田冬樹
近江ARS・叶 匠壽庵総務部長 池田典子
博物館 学芸員 横谷賢一郎
天台寺門宗・総本山 三井寺(園城寺)執事 福家俊孝
天台寺門宗・総本山三井寺(園城寺)長吏 福家俊彦
文芸評論家 安藤礼二
小花
佳つ春
槇里子
だん満
-司会-
近江ARSプロデューサー 和泉佳奈子
ーーーーー
-もてなし・しつらい・ふるまい-
塩崎浩司
角田 徹
松本慎一
中川幸一
-制作-
池田典子
野村智之
-意匠-
佐伯亮介
生地伸行
-照明-
MGS照明設計事務所
-進行-
宮本千穂
-PR-
中山雅文
-運営-
叶 匠壽庵
-会場-
寿長生の郷
ーーーーー
-映像-
伊賀倉健二
亀村佳宏
小川櫻時
-音響-
竹野智之
-撮影-
田村泰雅
-執筆-
阿曽祐子
ーーーーー
-監修-
松岡正剛
-企画-
和泉佳奈子
中村碧
-プロデュース-
百間
ーーーーー
-協賛-
叶 匠壽庵
-協力-
株式会社ミーアンドハーコーポレーション
-主催-
近江ARS

